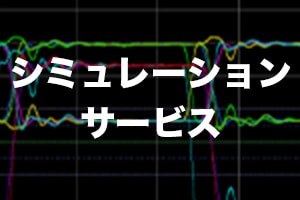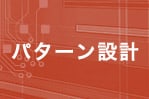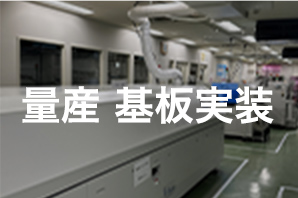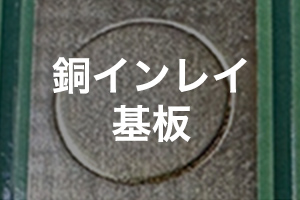プリント基板のパターン設計において、配線間の間隔(パターン間隔)は、
製品の性能と信頼性を大きく左右する重要な要素です。
パターン間隔を不適切に狭めてしまうと、ノイズによる誤動作や製品の信頼性低下を招く可能性があります。
最悪の場合、絶縁不良による短絡や漏電といった重大な故障につながることもあります。
一方で、過度に広い間隔は基板サイズの増大を招き、コストアップの要因となります。
このように、パターン間隔の設計は、使用する部品や基板材料だけでなく、
回路を流れる電圧を考慮する必要があるため、慎重な検討が求められます。
今回は、「失敗しない」電圧を考慮したパターン設計の考え方について解説します。
なぜパターン間隔が重要なのか?
パターン間隔が不適切な場合、主に以下の3つの問題が発生する可能性があります。
① ノイズによる誤動作
パターン間隔が狭すぎると、一方のパターンを流れる信号が、
意図せず隣接するパターンに影響を与えることがあります。
これはクロストークと呼ばれる現象で、ノイズの原因となり、回路の誤動作を引き起こす可能性があります。
② 絶縁不良
パターン間に印加される電圧が、その間の絶縁耐力を超えると、
絶縁破壊が発生し、短絡や漏電を引き起こす可能性があります。
これは製品の故障に直結するだけでなく、安全上の問題にもつながります。
③ 製品信頼性の低下
たとえ狭いパターン間隔でも初期動作が確認できたとしても、
長期使用や環境変化によって絶縁性が劣化し、将来的に故障やトラブルが発生する可能性があります。
これは製品の信頼性を大きく損なう要因となります。
安全規格への適合
情報通信技術機器やオーディオビデオ機器など、
多くの電子機器には安全規格(例:IEC62368-1)が適用されます。
これらの規格では、電圧に応じたパターン間隔の基準が明確に定められており、
設計者はこれを遵守する義務があります。規格に適合しない製品は、市場への出荷が認められない場合があります。
適切なパターン間隔の決め方:電圧と絶縁種別を考慮する
適切なパターン間隔は、回路で使用される電圧の大きさに依存します。
一般的に、高電圧が印加される箇所ほど、広いパターン間隔を確保する必要があります。
例えば、低電圧(3.3V、5Vなど)で動作する回路では、
比較的狭い間隔(0.15mm〜0.2mm程度)でも問題が発生しにくいことが一般的です。
しかし、12Vや24Vといったより高い電圧の回路では、同じ間隔では絶縁不良などの問題が発生する可能性が高まります。
さらに、パターン間隔は同じ電圧であっても、「基礎絶縁」と「強化絶縁」のどちらの絶縁種別が求められるかによって異なります。
- 基礎絶縁: 感電に対する基本的な保護を提供する絶縁構造です。
- 強化絶縁: 単一の絶縁で、二重絶縁と同等以上の高い感電保護機能を持つ絶縁構造です。より高い安全性や、過酷な環境下での使用が想定される機器に用いられます。
強化絶縁は、基礎絶縁よりも高いレベルの感電保護が要求されるため、
同一電圧であっても、より広いパターン間隔が必要となります。
一般的に、強化絶縁のパターン間隔は基礎絶縁の2倍程度に設定されます。
設計ミスを防ぐための電圧の可視化
プリント基板のパターン設計において、回路設計者とパターン設計者の間で、
各配線の電圧に関する認識のずれが起こることがあります。
特に、回路図を見ただけでは、全ての配線の電圧値を正確に把握することが難しい場合があります。
このような設計ミスを防ぐための有効な対策として、
回路図上で各電圧ごとに色分けをするなど、
電圧を視覚的に分かりやすくする方法が挙げられます。
これにより、パターン設計者は各配線の電圧を容易に認識でき、
適切なパターン間隔で設計を進めることが可能になります。
パターン設計ならアート電子にお任せください!
今回は、「失敗しない」電圧を考慮したパターン間隔の考え方をご紹介しました。
信頼性の高い基板製作には、電圧を考慮したパターン間隔をとることが必要です。
アート電子では、パターン設計をはじめ、
プリント基板の回路設計・基板設計、さらには実装を得意としています。
これまで培ってきた知見を基に、お客様のご要望に合わせて
最適な提案を実施し、高品質な基板設計をサポートしますので、
お気軽にアート電子にご相談ください。
また、当社ではその他の多数の技術情報をWEBサイトにアップしていますので、
ご興味をお持ちの方はぜひご一読頂ければと思います。
■ ノイズ対策に有効なシミュレーション~プレーン共振解析編~